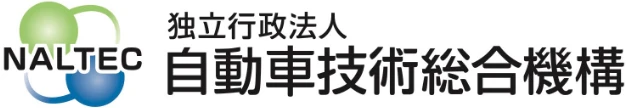よくある質問(FAQ):審査事務規程関係
よくあるご質問に対してお答えしています。
質問一覧
- Q1
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5
- Q6
- Q7
- Q8
-
Q1
「審査事務規程」とは何ですか?
A.
審査事務規程は、自動車が道路運送車両の保安基準に適合するかどうかの審査を行うため、次の事項を自動車技術総合機構の理事長が国土交通大臣に届け出たものです。
・審査の実施の方法に関する事項
・審査結果の通知の方法に関する事項
・その他の審査の実施に関し必要な事項 -
Q2
「審査事務規程」にはどのようなことが規定されているのですか?
A.
「審査事務規程」には、自動車の検査において、自動車の構造・装置が「道路運送車両の保安基準」に適合している状態であるかを判断するために必要な内容が具体的に規定されています。 詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。
-
Q3
古い自動車のための基準はありますか?
A.
「道路運送車両の保安基準」には、自動車の製作年月日などに応じて必要な事項が定められています。(道路運送車両の保安基準第58条) 当法人における自動車の製作年月日などに応じた規定は、「審査事務規程」に「適用関係の整理」として規定しています。
-
Q4
自動車の製作年月日の決め方はありますか?
A.
自動車の製作年月日は、初めて検査又は登録された日としていますが、自動車製作者が発行した書面などがある場合は、その書面に記載された日付を自動車の製作年月日とすることがあります。 詳しくは、「審査事務規程」をご覧下さい。(4-5 参照)
-
Q5
「不適切な補修」とは何ですか?
A.
基準に不適合な状態にある自動車の構造、装置などの補修が一時的なものにならないようにするため、「審査事務規程」において、「道路運送車両の保安基準」に適合しない補修等を「不適切な補修」として具体的に示しています。(4-4 参照) 例として、灯火器のレンズの破損を粘着テープにより補修したものは、「不適切な補修」に当たります。
-
Q6
「最低地上高」とは何ですか?
A.
最低地上高は、自動車の接地部以外の部分と地面との間に必要な最低限の間げきであり、車高を低くした乗用車などの最低地上高は、空車状態で測定した値が次の(1)から(3)までのそれぞれの値以上でなければなりません。
(1) 自動車下面の全面で9cm
(2) 自動車の軸距(ホイールベース)に応じて、次式により得られる値 (ホイールベース)×1/2×sin2°20’+4 【sin2°20’=0.04】 例:ホールベース250cmの場合は9cm
(3) 自動車の前軸から前方の距離及び後軸から後方の距離(オーバーハング)に応じて、次式により得られる値 (オーバーハング)×sin6°20’+2 【sin6°20’=0.11】 例:オーバーハング50cm部分の場合は7.5cm 詳しくは「審査事務規程」をご覧ください。(7-3、8-3 参照) -
Q7
ディーゼル黒煙検査とは、どのような検査ですか?
A.
「道路運送車両の保安基準」に規定されているディーゼル自動車のアクセル全開時の黒煙を目視及び機器により確認する検査です。 詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(9-7 参照)
-
Q8
原動機用蓄電池の技術的要件(UN R100のREESS要件)とは何ですか?
A.
電力により作動する原動機を有する自動車に備える原動機用蓄電池(駆動に係る電力を供給するための電気的に接続された電力貯蔵体及びその集合体をいい、作動電圧が直流60Vを超え1,500V以下又は交流30V(実効値)を超え1,000V(実効値)以下のものに限る。)は、原動機用蓄電池の技術的要件(UN R100の充電式エネルギー貯蔵システム(REESS)の要件)に適合していなければなりません。 詳しくはこちら こちら (133.04 KB)をご覧ください。